INTERVIEW
研究者インタビュー
2025.09.16
研究者インタビュー
Vol.79
過敏性肺炎研究の発想で感染症を解く。基礎・疫学研究に着手
第三期プロモーター教員
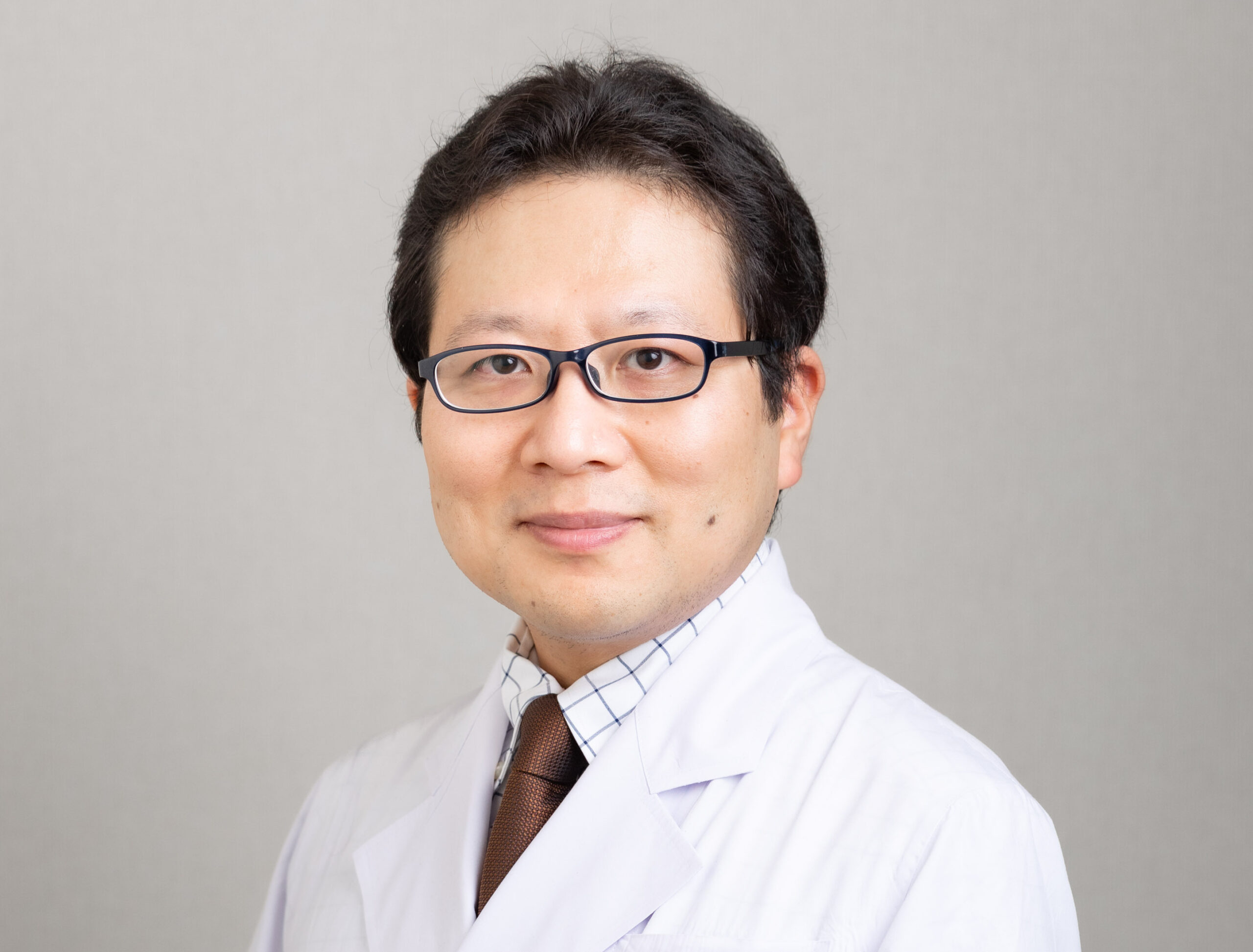
ウイルスや細菌(さいきん)などの病原体が私たちの体内に侵入することで発症する感染症。咳や発熱を発症し、乳幼児や高齢者では重症化することも。人から人への感染だけでなく、土や水に含まれる菌からでも感染症になるケースもあり注意が必要です。今回は、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などの病原体や抗酸菌の疫学解析といった感染症の研究に従事する園田史朗先生にインタビュー。現在の研究内容や産学連携で実現してみたいことを聞きました。
- プロフィール
-
東京科学大学
肺免疫治療学講座
寄附講座助教
園田史朗先生
私が聞いてみました
-

-
医療イノベーション機構イノベーション推進室シニアURA(特任教授)
インタビュアー詳細
山田周作
研究について
先生の所属分野について教えてください。
- 園田:
- 現在は肺免疫治療学講座に所属しています。2020年10月に設置された寄附講座で、当時流行していた新型コロナウイルス肺炎の重症化因子探索や、難治性気管支喘息・過敏性肺炎・肺線維症の治療法開発など免疫に関与する疾患の解明に力を入れています。
2025年10月頃に呼吸器内科に配属予定になっており、感染症を主軸とした研究を引き続き行う予定です。
学生の頃はどのような研究をされていましたか。
- 園田:
- 大学院生の頃は、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の病原性を解明する研究をしていました。黄色ブドウ球菌は人の鼻腔や咽頭などに生息しており健康であれば無害とされてきました。MRSAは細菌を退治する抗生物質に耐性があり、抵抗力の弱い人に感染しやすく発熱、嘔吐、傷口の化膿、肺炎といった呼吸器感染症を引き起こす原因となります。さまざまな薬に耐性があるため、重症化しやすいのも特徴です。それが、2000年に入りアメリカを中心に健常者も感染する高病原性のMRSAが出現したことで、感染力・病原性・耐性を兼ね備えた菌として問題になりました。
MRSAについて研究していたんですね。研究の魅力をお聞きしたいです。
- 園田:
- 1960年代に抗生物質のメチシリンが欧米で使用され始めた後、間もなくしてMRSAが発見されました。歴史は古くさまざまな研究が行われている菌種ですが、1980 年代には日本国内でも確認され、2000年代に米国で毒性の高いMRSA株(USA300)が流行するなど常に新しい変化を見せ、日進月歩の戦いです。
MRSAは菌の中でも増殖サイクルが短く、研究のトライ&エラーがしやすいのも私の性分に合っていたこともあり、研究にどんどんハマっていきましたね。
現在の研究内容、また今後はどのような研究に取り組む予定ですか。
- 園田:
- 統合呼吸器病学分野の宮崎泰成教授が過去に和興フィルタテクノロジーと産学連携でリゾチーム・キトサンオリゴ糖複合体(商品名:「LYZOXⓇ(リゾックス)」)の細菌に対する抗菌作用について共同研究を行った経緯があります。MRSAの薬剤耐性菌にも効果があるとされ、この研究内容を応用しようと思い研究計画を立てている段階です。
また、抗酸菌にも関心があります。抗酸菌とは、大まかに結核と結核以外の感染症(非結核性抗酸菌症)に分類されます。私が注目しているのは非結核性抗酸菌。土や水、動物など自然の中に広く存在しており、近年日本や東南アジアでの患者数は増加傾向です。その他には、アレルギー学会から研究費を拠出してもらい、過敏性肺炎になった患者の肺を菌叢解析し、細菌の種類や割合が病状に与える影響も明らかにしたいと考えています。
研究の中でも特に非結核性抗酸菌に力を注いでいるとお聞きしました。
- 園田:
- 非結核性抗酸菌は100種類以上存在しており、そのうち数十種類が人に感染すると言われています。咳や痰、息切れ、胸痛に加えて、病状が悪化すれば肺炎など人体に大きな影響を与える病気です。非結核性抗酸菌は不明なことも多く、診断や治療方法もわずかしか確立されていないため、基礎研究に携わる人間としてやりがいと責任を感じています。

非結核性抗酸菌に関して具体的にどういったところを深掘りしていく予定ですか。
- 園田:
- 大きく3つあります。まず1つ目に、薬剤耐性の影響です。薬での治療では、複数の抗生物質を同時に飲むことが多く、しかも1年以上での長期の治療になるケースがほとんど。そのため、副作用も懸念事項としてあげられます。どの抗生物質が効果的で、身体に影響が少ないかを見極めていきたいです。2つ目は発症原因の特定。本学は過敏性肺炎の研究が進んでおり、家の中にあるカビやホコリなど微小な物質を特定する技術に長けています。その技術を応用して患者の家を調べて、原因となる菌を見つける予定です。最後に、LA-MRSAという概念の応用をしたいです。LAとはLivestock-associatedの略ですが、要すると家畜関連です。家畜は感染の予防に抗生物質の使用が広まっており、実は耐性のある菌がいるのではと言われています。実際にLA-MRSAは人獣共通の感染症として注目されています。「生活環境の中に存在している菌であればMRSAだろうとNTMだろうと家畜にも存在しているのでは」というが私の見立て。家畜の一部分を譲り受けて、人体と家畜を比較しつつ非結核性抗酸菌の生息状況を調べてみたいですね。これにより今後拡大するかもしれない抗酸菌や、出所不明の抗酸菌の正体が掴めるかもしれません。
感染症の研究を始めた決めた理由はありますか。
- 園田:
- 指導員の先生に「医学論文の本質を理解したいのなら、執筆者側の立場になって意図を汲み取る必要がある」とアドバイスを受け、それならば実際に研究者になってみようと奮い立ち今の道に進みました。大学院生時代に感染症の講座を聞いて魅力に取り憑かれ、本学に在籍しながら国内留学の形で東邦大学の医学部微生物・感染症学講座の舘田一博教授の元で基礎から学びました。
大学院卒業後は栃木県にあるインターパーク倉持呼吸器内科で呼吸器内科の医師として勤務した経験もあります。病気に苦しむ人を最前線で治療する仕事は充実感がありましたが、慢性化・重症化する患者の姿を見て病気の原因を特定し、そもそも感染症にかかる人を減らしたいという気持ちが芽生えて研究の道に戻りました。
産学連携について
今まで産学連携のご経験はありますか。
- 園田:
- 先ほど話にもでましたが、和興フィルタテクノロジーと一緒にリゾチーム・キトサンオリゴ糖複合体(商品名:「LYZOXⓇ(リゾックス)」)という抗菌物質の効果の研究に関わっていました。MRSAを含むさまざまな菌、さらには菌以外の病原微生物に他する幅広い抗微生物作用に期待を寄せています。

- 身近にいる菌は知られていないだけで特性や効能が分かれば興味を持つ企業もいるはず。企業側にプラスとなる情報を発信して、たくさんの人が使いたい&欲しいと思える機能を社会実装するサポートもやってみたいですね。
企業との共同研究で学びとなった体験はありますか。
- 園田:
- 調査したレポートを企業に提出すると、理想通りの結果にならなくても「こういう性質が発見できたので、別のアプローチで商品化ができるかもしれない」と従来の発想にとらわれない柔軟性を持った視点は、産学連携を通じて勉強になった点です。前例や慣習にとらわれず、研究に取り組みたいと心を改め直すきっかけになりました。
どのような企業と一緒に共同研究をしてみたいですか。
- 園田:
- 抗酸菌の研究では、畜産業界の企業ですね。他には感染の分野でも吸入治療が出てきていますが、一体どこまで届いているのかわからない。理屈で言えば、ミクロな部分の解明(組織学的・病理学的)とマクロな構造の解明(解剖学的・CT検査など)、そして、マクロな動き(スパイロメトリーなど)は計測できています。これらを統合し、コンピューター上でシミュレーションできるようになれば、どのような患者にどのような薬が合致するか、さらには研究すべき薬剤の粒子径が絞れる可能性があります。そういった、AI(人工知能)や高速演算処理が可能な画像診断ソフトを開発している企業と一度お話できたら嬉しいです。
イノベーションプロモーター教員について
プロモーター教員になったきっかけを教えてください。
- 園田:
- 同じ呼吸器内科にいる石塚聖洋寄附講座助教から「交流会やイベントを通じて企業や他分野の研究者の方々とつながれる」と聞き、魅力を感じて引き受けました。ぜひ畜産農家、酪農関係に強いアカデミアの方をセミナーに呼んでもらい、連携できるように働きかけていきたいです。医療イノベーション機構の皆さんとも情報交換を定期的に実施し、企業を紹介してもらえるような協力体制を作っていきたいですね。
旧東京工業大学と統合したこともあり、工学や情報系の先生とも感染症研究を通じて新薬の開発や既存資源の再活用、新技術との融合など実用性を意識したイノベーションを起こすことも密かな目標です。
最後に
研究や産学連携についてお教えくださりありがとうございました。休みの日はどのようにリラックスして過ごされていますか。
- 園田:
- カピバラが好きで、栃木県に住んでいた頃は那須どうぶつ王国にある「カピバラの森」に足しげく通っていました。全国でもカピバラと触れ合ったり、エサやり体験ができる場所は珍しくオススメです。カピバラはゴワゴワした毛が特徴的な世界最大のネズミで、泳ぐのが得意。シュールで愛くるしい表情は、見ているだけで癒されます。私の下の子どもが1才と小さいので、もう少し大きくなったら家族でカピバラに会いに出かけるのが夢ですね。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください
- 医療イノベーション機構
openinnovation.tlo@tmd.ac.jp

CONTACT
東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。
