INTERVIEW
研究者インタビュー
2025.01.30
研究者インタビュー
Vol.68
企業との産学連携で裸眼立体視モニターを活用し術野をリアルタイムで再現 若手育成につながる教材開発にも熱意
第三期プロモーター教員
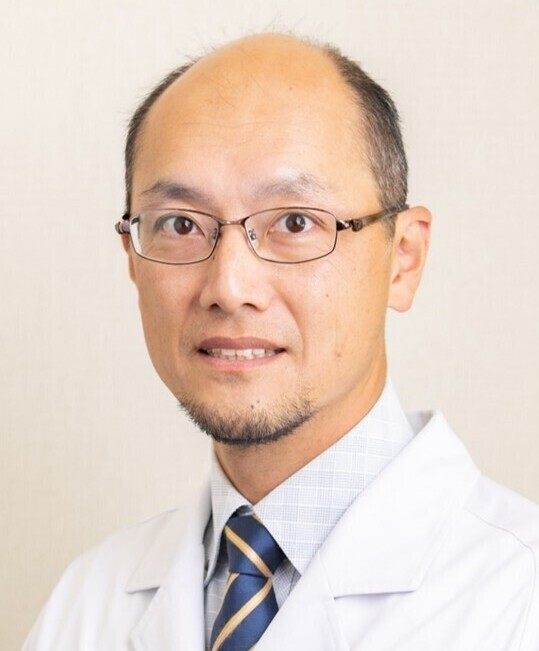
日々変化する子どもの身体。「子どもは大人のミニチュアではない」と言われるほど、小児期特有の病気が存在し、治療には専門的な知識や技術が求められます。今回は、数少ない小児外科医の指導医の資格を持つ岡本健太郎先生にインタビュー。若手医師の育成にかける思いや、産学連携での研究内容についてお聞きしました。
- プロフィール
-
医学部附属病院
総合外科学分野小児外科学
准教授
岡本健太郎先生
私が聞いてみました
-

-
医療イノベーション機構イノベーション推進室
インタビュアー詳細
URA(特任准教授) 磯部洋一郎
研究について
所属分野について教えてください。
- 岡本:
- 総合外科学分野小児外科の診療科長として、新生児・小児の治療や手術を担当しています。「内科=小児科」、「外科+脳、心臓、整形外科を除いたその他の診療科=小児外科」とイメージしてもらえればわかりやすいでしょう。病気や臓器は多岐にわたり、慢性的な便秘や急性虫垂炎のような急性疾患など治療対象はさまざま。年に数回ですが、腸閉鎖症(十二指腸・小腸・結腸)や胆道閉鎖症など稀少な先天性疾患も執刀しますし、小児固形腫瘍(小児がん)では、手術、薬物療法、放射線治療などを組み合わせた集学的治療を小児科・新生児科・麻酔科・産婦人科と連携しながら行います。子どもの臓器は働きも未熟で大人の身体では当たり前の常識が通用しないこともしばしば。だからこそ、お子さんや保護者の視点に合わせた治療を提供できるように日々研鑽に励んでいます。
小児外科医として活動する傍ら、どのような研究を行っていますか。
- 岡本:
- 包括連携協定を締結しているソニーとの共同研究チームの一員として、空間再現ディスプレイの医療応用を目指した開発に従事しています。具体的には、手術の様子を3Dカメラで撮影し、離れた場所で、空間再現が可能なディスプレイを通して術野をリアルタイムで視聴できるようにするという研究です。小児外科の研修医たちに手術の手元部分を再現した映像を視聴してもらうことで、教育効果を高め、解剖理解につながります。

- 難しい手術内容でもモニターに映し出される映像は精度がよく、将来的には遠隔地での治療にも応用が可能。最近では、手術現場の音声など映像以外の素材の活用方法を模索しています。
VR(Virtual Reality:仮想現実)を用いた漢方医学の学習教材も開発予定だと聞きました。
- 岡本:
- 自力では飲みづらい漢方を服用している患者さんの自宅を360°カメラで撮影して、遠隔でも在宅医療の現場を学べる教材を教育機関と連携して作成する予定です。研修医の先生は在宅医療を勉強するチャンスがほとんどないため、社会に羽ばたくまでに理解を深めておけば日本の在宅医療の裾野も広がるはずと考えています。
本学のベストティーチャー賞を受賞したこともあるそうですね。
- 岡本:
- 名誉ある賞をいただきました。研究を通して、優秀な人材を輩出できれば嬉しいですし、結果として医学界の発展に少しでもお役に立てれば光栄です。
岡本先生が小児外科医を目指した理由をお聞きしたいです。
- 岡本:
- 大学6年生の頃に小児外科の研修担当だった先生に感銘を受けて志を固めました。卒業後は栃木県にある獨協医科大学病院で小児科医として勤務し、当面は栃木県で暮らすだろうと家も購入していました。ところが、2016年に本学で小児外科を立ち上げる話が出て私に声がかかったんです。とても迷いましたが「卒業生として恩返しをしたい」と思い、新幹線通勤で孤軍奮闘しながら8年の歳月が経ち、今では8人の後輩が所属するチームになりました。
やりがいを感じた実体験などございますか。
- 岡本:
- 生まれつきお尻の穴がない鎖肛(さこう)と呼ばれる先天性の病気を持ったお子さんの手術を担当したのですが、生後間もない頃から高校2年生になった現在までたくましく成長していく過程をご両親とともに「わが子」の視点に立って見届けられたのは貴重な経験でした。大きな責任が伴う仕事ですが、「排便も上手くコントロールできて、修学旅行も楽しめました!」という喜びの声を聞いた時は努力が報われた気持ちでしたね。
産学連携について
企業との共同研究に関して教えてください。
- 岡本:
- 私の同期で第2期プロモーター教員でもある腎泌尿器外科学分野の吉田宗一郎先生が、ソニーとの共同研究で、視線と音声によってディスプレイに投影された内視鏡映像をコントロールするユーザーインターフェースを開発していました。その技術を、鼠径(そけい)ヘルニア(脱腸)の腹腔鏡手術に導入し、改善点などをフィードバックした経験があります。腹腔鏡手術では助手が術者の視野に合わせてカメラを移動するのですが、術者の目線に合わせて自動追尾や拡大が可能であれば1人で手術が完結します。手ブレによるミスや助手への細かい指示が不要になり、他の手術にも応用できる素晴らしい共同研究でした。
産学連携で気をつけている点や大切にしている点はありますか。
- 岡本:
- 医学の専門用語は難解で相手に意図が伝わらない可能性があります。そのため、言葉を噛み砕いて誰にでも理解できるように話すことを心がけています。月に数回ある企業との定例会議は、オンライン会議がほとんど。お互いのゴールを擦り合わせたり、研究の進捗状況を肌で感じてもらうために、手術の現場に足を運んでもらえるように計画を立て、スケジュール調整にも配慮しました。企業は研究者のアイディアを実現する技術を数多く所有している。だからこそ、研究者である私たちは常識にとらわれず、チャレンジングな研究内容だったとしてもしっかり言語化し、企業にプレゼンすることが産学連携の第一歩として大事だと思います。
大学統合による相乗効果も楽しみですね。
- 岡本:
- 期待は大きいですね。腹腔鏡手術で使用する鉗子の強度について旧東京工業大学の先生たちと協議したのですが、視座が高く製品化まで検討していた。もし研究チームに加わっていただけたら、間違いなくイノベーションを起こせると感じました。
イノベーションプロモーター教員について
プロモーター教員になった経緯をお聞きしたいです。
- 岡本:
- 第2期プロモーター教員で耳鼻咽喉科学分野の伊藤卓先生が旧東京工業大学の先生方と仲がよく、たまたま食事会に誘われたのですが、AI(人工知能)など異なる領域の最前線で活躍する方々の話が新鮮で面白かった。私自身の研究を深めるきっかけにもなりますし、知り合いの研究者や企業をマッチングできれば新しい価値が創造できると考え、プロモーター教員に手を挙げました。新しいものはとりあえず試してみたい性格の私にはぴったりの役割かもしれません。

医療イノベーション機構に期待することはありますか。
- 岡本:
- OIセンターは、産学連携、知財管理、起業のために必要な企画立案、実務や研究のサポートをワンストップで行う組織です。共同研究だけでなく、受託研究や秘密保持契約のサポートも万全。産学連携は書類や資料の作成、契約など事務作業が意外と多いので、磯部さんのような経験豊富な方々に指南してもらえると安心です。課題解決の糸口を探す場として、無料のオンラインセミナー(tip BBセミナー)で他分野の研究に触れられるのもいいですね。以前、統合教育機構イノベーション人材育成部門主催の「医療DXイノベーション人材育成プログラム」に参加したのですが、講師の方の専門性が高く、向上心のある人が集まっていて刺激を受けました。「アントレプレナー育成プログラム」「データサイエンス人材育成プログラム」など起業や新規事業開発に関心がある人向けの授業も開講しているので、参加をおすすめします。
最後に
最後に先生の趣味を教えてください。
- 岡本:
- 学生時代は陸上部でした。今でも気分転換を兼ねて仕事終わりに皇居の周りを走ったり、休日には子ども達を連れて筑波山に登ることもありますね。私たちの研究室は26階建てのM&Dタワーにあるのですが、朝早く来て階段で最上階まで上り、スカイツリーを撮影するのが日課になっています。
小学6年生、中学2年生、高校2年生の3人の子どもがお昼ごはんに弁当が必要な時は、妻と交代制で料理を作ることも。卵アレルギーなので卵料理は避けていたのですが、弁当作りにハマったおかげで「卵焼きは見た目もきれいで美味しい」と子ども達に褒められるまで成長しました。長女も陸上部で大会にも出場しているので、応援にも弁当作りにも熱が入ってしまいます(笑)。

先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
医療イノベーション機構
openinnovation.tlo@tmd.ac.jp
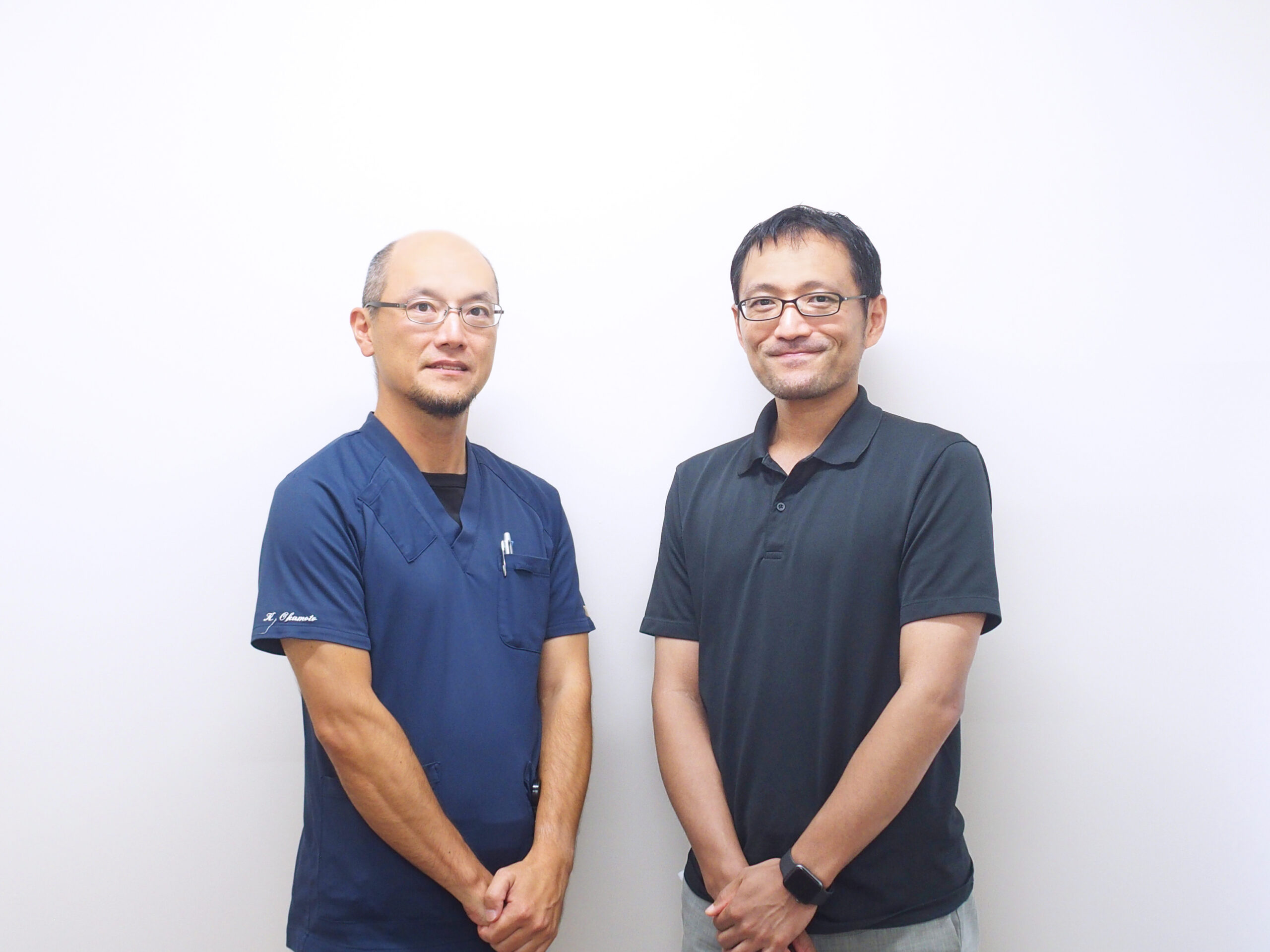
CONTACT
東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。
