INTERVIEW
研究者インタビュー
2020.12.17
研究者インタビュー
Vol.21
脳神経外科手術に統合ナビゲーションシステム導入を計画
第一期プロモーター教員
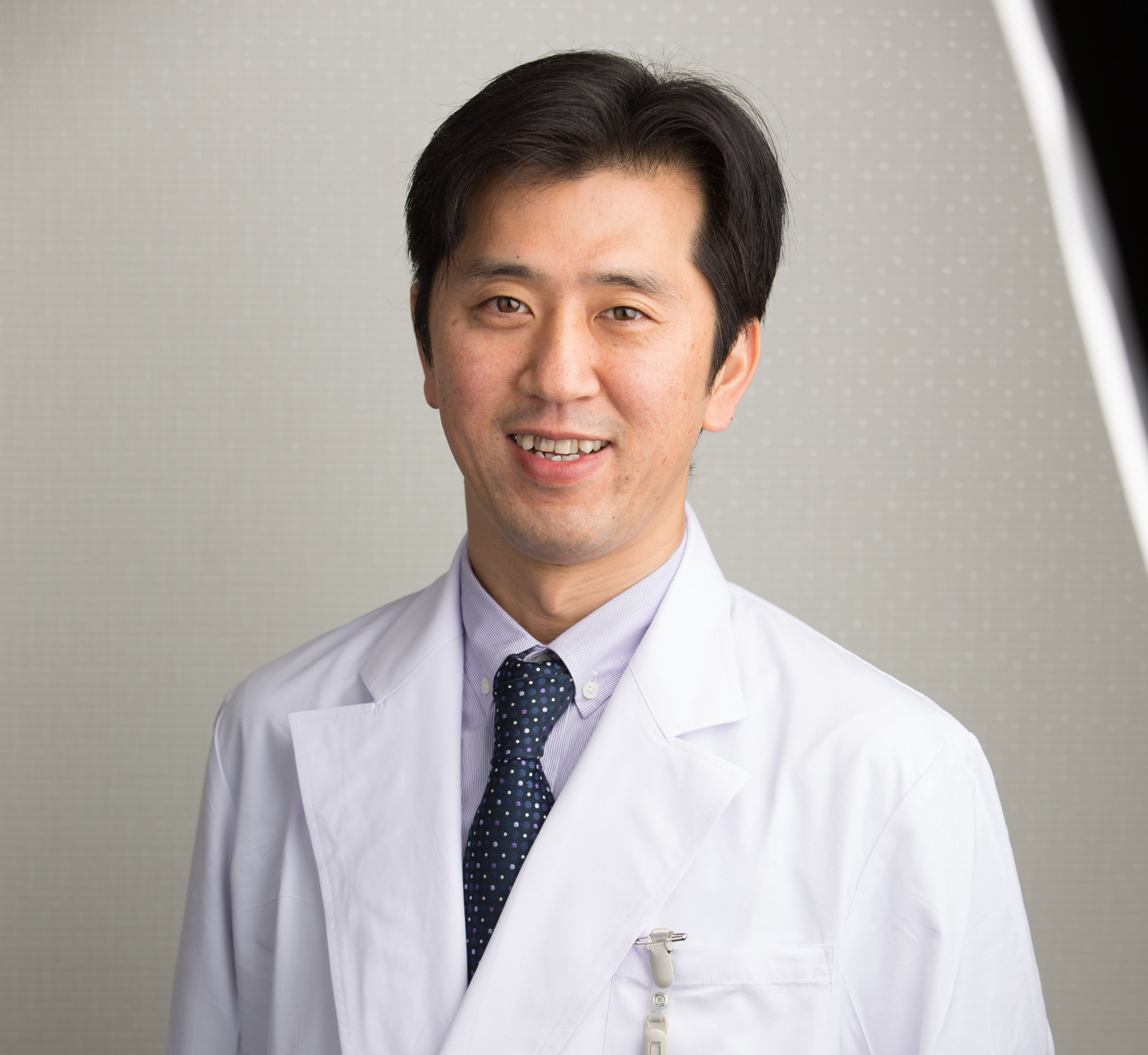
脳神経外科として25年のキャリアを持つ田中洋次先生のインタビュー。患者の脳と病変部位をリアルに再現し、手術を受ける患者と現場に立つ医者の負担軽減を目指しています。ソニーさんとの産学連携で得た学びを活かした今後の研究方法についてお話をうかがいました。
- プロフィール
-
医学部附属病院
脳神経外科
講師
田中洋次先生
研究分野について
先生が脳神経外科医になったきっかけを教えて下さい。
- 田中:
- 1995年に東京医科歯科大学を卒業して、脳神経外科学教室に入局しました。外科的な治療や手術に興味があったこと、外科系診療科の中でも特に脳は解明されていない領域も多いので、自分でも何か新しい発見ができるのではないかと思い、脳神経外科を選びました。
病院で脳神経外科医として勤務して手術に何度も関わる中で、後遺症を残さないよう可能な限り脳の機能を維持しながら、腫瘍を切除しなければいけないなど、脳はとても繊細な臓器だと改めて気付かされました。
手術の際に、脳にできた腫瘍や血管の詰まりなどの病変は、深部に隠れていることもあります。そのような場合、脳の表面から見ただけでは分からないので、どうやって目的地にたどりつけば良いか悩むこともあります。脳の神経機能も見ただけでは切っても大丈夫か、残しておくべきかの判断ができません。見えない敵と戦う手術は集中力が必要とされるため、術者が安全で効率よく手術できるようにしていきたいと考えています。
私の夢は、手術中に1つのディスプレイ上で脳の映像と機能を表示させて、切除しても大丈夫、脳の血流が悪化しているから処置が必要、などが簡単に分かる統合ナビゲーションシステムを作りたいと思っています。
ナビゲーションのある手術は、どのように行われるのでしょうか。
- 田中:
- 車のカーナビが似ていますね。MRIやCTなどの画像を地図代わりにして、術者が脳のどの部分を触っているのかを画像上にリアルタイムで示してくれるので、神経や血管といった重要な組織を傷つけることなく手術が行えます。しかし実際に手術でナビゲーションを使う際には、手術台の横にモニターを置いて、そこに映されたナビゲーションの画像と、顕微鏡や内視鏡の映像を見比べながら、手術をする形式がほとんどです。これだとモニターの画像を確認するために、その都度手術を止めて視点を変えないといけません。
今後は、術者が手術顕微鏡で見ている視野の中にさまざまな情報を表示させて、それを見ながら手術することで、機能性・安全性がより高まると期待されます。
脳神経外科手術の最近のトレンドについて教えて下さい。
- 田中:
- 脳神経外科では直接目で見る顕微鏡に代わり、「外視鏡」が導入されることも増えてきました。外視鏡とは、術野を外から撮影し、特殊なメガネを着用してモニターの3D画面を見ながら手術をします。顕微鏡と同じ画質で撮影した患部を立体的に見られますし、機器も小さいので自由な空間が増えて、術者が楽な姿勢で手術できます。
とても便利な機器ですが、顕微鏡で手術していた人達にはモニター画面を見ながらの作業には慣れていませんし、立体感覚の捉え方が違うため、好みが分かれるところです。外視鏡が一般的に使われ始めるのはまだ先だと思いますが、脳神経外科の手術は10年経つとかなり様変わりするので、どうなるか楽しみですね。外視鏡のモニター画面に、腫瘍や神経機能の画像を重ね合わせた統合ナビゲーションシステムもできるでしょうね。

ヘッドマウントディスプレイを装着して経鼻内視鏡手術(下垂体腫瘍の手術)を行っている様子
ナビゲーション研究の面白いポイントはどのようなことでしょうか。
- 田中:
- 手術中に脳の表面から見ただけでは見つけられなかった異常が、ナビゲーションを使って発見できた時は、感動がありますね。「この場所に腫瘍がある」と分かったら摘出に集中すれば良いので、手術を行う先生の負担軽減にもつながると信じて研究をしています。
研究をしていて気付いたことはありますか。
- 田中:
- 我々の教室では、手術中のデータ解析や、患部と画像をリアルタイムに重ね合わせるようなシステム作りが、現時点ではあまり実現できていません。これらのシステムを、試験的に手術に導入している大学病院もあるので、本学でも行っていきたいですね。
また、私達が理想とするナビゲーションシステム実現のためには、画像処理や解析のためにプログラムを組む必要があります。色んな情報を1つに統合しようと思った時に、医師の力だけではできません。画像を重ね合わせる技術にしても、顕微鏡や内視鏡で見ている映像を手術中で目の見える範囲に落とし込む作業でも、技術力のある企業やエンジニアの方の力をお借りする必要がありますね。
産学連携について
産学連携で企業と共同で研究をした経験について教えてください。
- 田中:
- 企業と一緒に製品を作ったという実績はまだありませんが、企業が開発した製品を用いて有用性をチェックすることは、ソニーさんと行いました。
ソニーさんが開発した医療用ヘッドマウントディスプレイを、内視鏡手術で使ってみて、使用感のアドバイスをさせていただきました。 ソニーさんのヘッドマウントディプレイが便利だと泌尿器科の先生から教えてもらい、脳神経外科でも試してみることになったのが始まりでした。その際は使用した感想をまとめて伝えるだけだったのですが、立体的に見えるような視野の角度を調整したり、着け心地など具体的なフィードバックをして、製品のアップデートに役立つことができたのではないかな、という思いがあります。
また、ソニーさんとは手術中に脳の血流を測る技術についても共同研究を行っています。
脳の血流はどのように測るのでしょうか。
- 田中:
- 手術中に脳の血管の流れをレーザー光で測定します。血管にプローブ(探触子)を当てて血の流速をエコー(超音波)で測る製品はありますが、局所でしか使用できないので脳全体は確認できません。レーザー光での測定法ならもっと広範囲でリアルタイムに情報が取れるので、臨床応用が可能になれば、例えば動脈瘤の手術でクリップをかけた際に、周囲の血管を閉塞していないかどうかの確認が容易になります。
従来の術中血管撮影の方法としては、蛍光造影剤を注射して、術野に特定の波長の光を当てて、造影剤が血管から組織に入っていく様子を見る技術があり、顕微鏡にも搭載されています。ですがこの方法だと、造影剤を1回使うとしばらく使えないという欠点があります。また蛍光造影剤が流れる様子は、術野外のモニターにしか映し出せないため、術者はビデオで録画したものを後から見返して判断するしかないなど、課題点もあります。これからの医療を支えていくために医療技術の進歩や新しい取り組みが求められています。
MRI画像などの情報を手術中に活かすためにはどのような技術が大事ですか。
- 田中:
- データや画像を、術者の見やすいように視野に落とし込む技術が重要だと思います。もちろんMRIなどで新しい撮影法を開発して、画像としてよりハイクオリティに見える化することも大事ですが、手術に関して言えば、術者が手術中に使いやすいシステムがなければ、医療機器として普及するのは難しいかもしれませんね。
さまざまな技術が必要なのですね。
- 田中:
- 手術を経験すると、この手術ではどの画像情報が有用だとか、術者の顕微鏡視野に画像を表示させるときに、邪魔にならない視野の比率といったノウハウが蓄積されます。手術中の場面に応じて必要な情報を選択して提示させて、それを見ながら安全にできるようなシステムを作りたいと思っていて、一緒に製品化を目指して下さる方や企業の手助けがあると嬉しいですね。
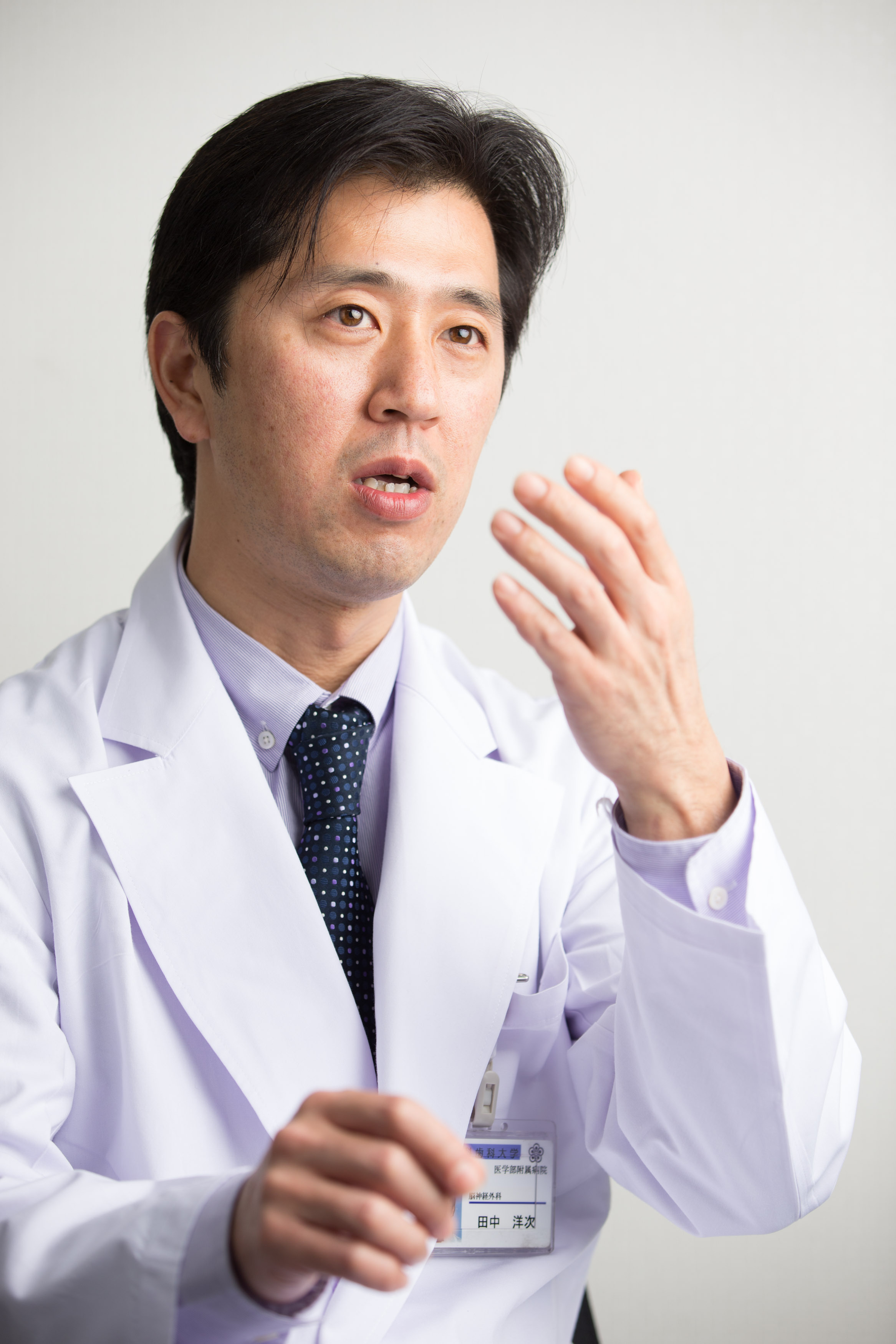
研究から製品化に進む過程は興味深いですか。
- 田中:
- 新しい医療機器が開発されるプロセスは全く知らない世界でした。今まではすでにある機器や設備しか使ったことがないので、医療機器として認可されるまでにどういう道を辿るのかを学べるのは楽しいですね。本学にはオープンイノベーション機構や産学連携研究センターがあり、企業と研究者とのマッチングがしやすくなり、新しい共同研究に取り組みやすくなったので、私もチャレンジしてみたいという気持ちが強くなっています。1人ではできないことなので、色んな人と関わり合いながら、社会に貢献する医療機器やシステムを作っていきたいですね。
脳神経外科では企業との連携は少ないのでしょうか。
- 田中:
- 私個人は外部との連携の機会はあまり多くない印象です。他の大学病院では、同じ大学の工学部と医工連携をしたり、企業と連携をして素晴らしいシステムが世に出ています。プロジェクションマッピング技術や拡張現実(Augmented Reality)、仮想現実(Virtual reality)を活かして手術をガイドするシステムや、手術室全体をヘッドマウントディスプレイのような空間にする技術を開発しているところもありますね。
企業や医者ではない方が手術を見学することもできるのでしょうか。
- 田中:
- 現在の共同研究では何度か手術室に入ってもらって一緒に見学、計測してもらっています。もちろんその場合には、患者に趣旨を事前に説明して手術室に入る許可を得ています。
プロモーターとしての取り組み
イノベーションプロモーター教員になった理由を教えて下さい。
- 田中:
- 脳神経外科の先生には産学連携について詳しく知らない方もいらっしゃるので、研究内容の製品化や企業とのコラボーレーションをまず自分が経験してみて、「機器開発のための共同研究のやり方」を他の先生にご紹介できる機会も、イノベーションプロモーター教員としてやってみたいですね。
経験を伝えていく「場」をどのように作りたいですか。
- 田中:
- 自分の医局以外に、学内でも同時進行で「場」作りをしたいですね。同じ脳神経外科の先生たちには、ほとんどリアルタイムで経験を共有するチャンスがあります。学内ではイノベーションプロモーター教員の発表会で、自分自身の経験をお話しできればと思います。オープンイノベーション機構のウェブサイトに導入事例などもあるので、さまざまな手法で対外的に経験やノウハウを発信していけたら良いですね。
オープンイノベーション機構でサポートしてもらいたいことはありますか。
- 田中:
- 企業を紹介してもらったり、臨床研究をするにあたって手続きをサポートしてもらいたいと思っています。進捗管理など全体のマネジメントもしていただけると助かりますね。
また、企業と行う共同研究では、研究で成果が得られた後に、製品化する道標を示してもらいたいですね。新しい機器として市場に出回ることになるので、顕微鏡など医療機器に組み込むためのメーカーなどとの接点作りもお願いしたいですね。
最後に
先生のご趣味について聞かせてください。
- 田中:
- 学生の頃から硬式テニスをやっています。留学した時はテニスチームに所属もしていました。帰国してからは子供用のラケットも買って、帰省した際などに子供と細々テニスをして楽しんでいます。最近では大きな大会で日本人選手が活躍しているので、試合結果に一喜一憂しながらも楽しんでいます(笑)。大坂なおみ選手の活躍は素晴らしいですね。錦織圭選手など男性陣も含め、応援し続けています。

- トロフィーは以前に務めていた関連病院で開催されたテニス大会で、循環器内科の先生とダブルスを組んだ時にもらったものです。
ありがとうございました。
CONTACT
東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。
