INTERVIEW
研究者インタビュー
2020.12.03
研究者インタビュー
Vol.20
神経活動電位の高速伝導装置・髄鞘の分子機序解明と応用を目指して
第一期プロモーター教員
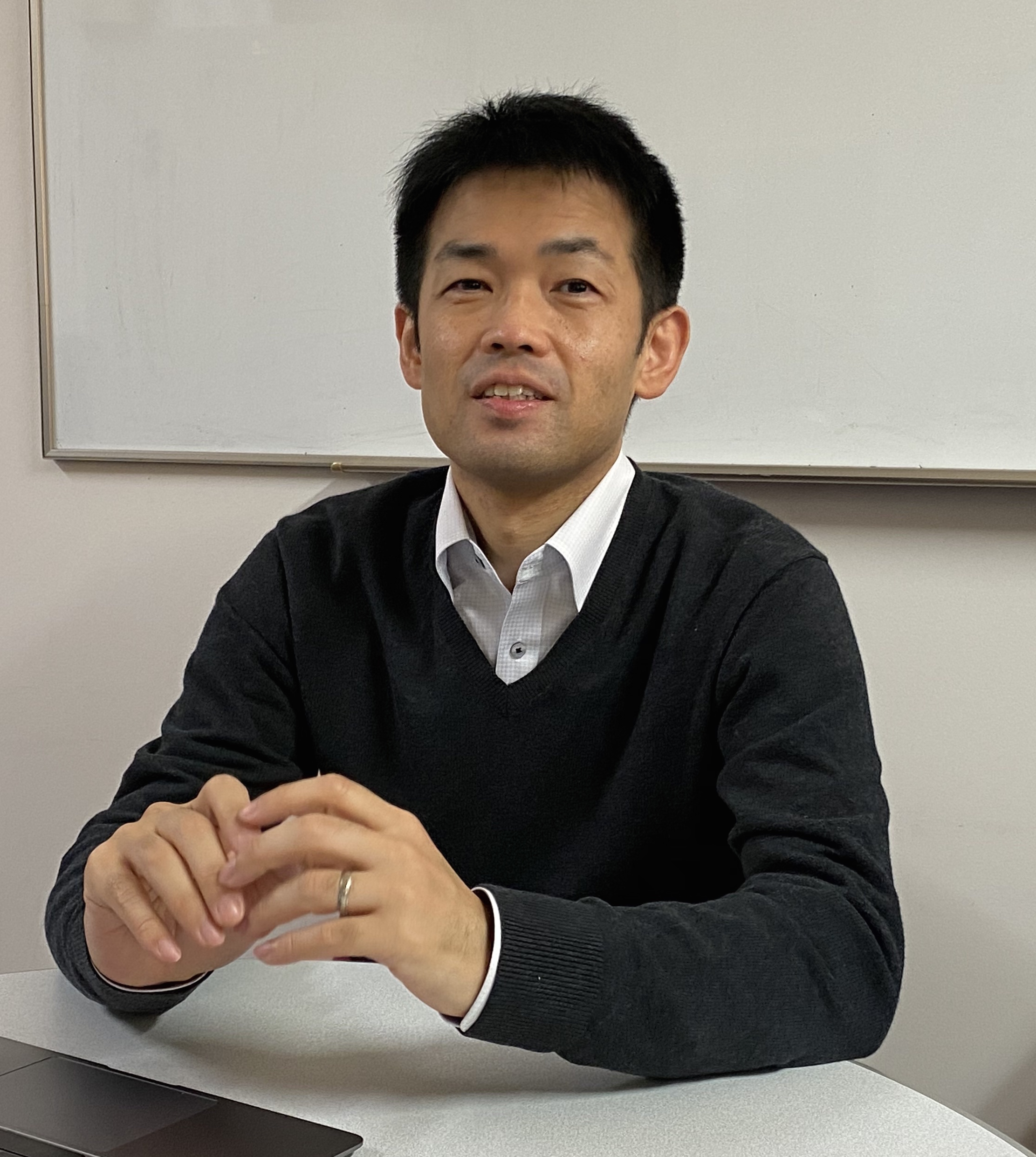
中枢神経の髄鞘形成を担う細胞と細胞または細胞と細胞外マトリックスをつなぐ膜タンパク質を研究する鈴木喜晴先生のインタビュー。産学連携を通じて基礎研究を応用した製品開発や難病の治療法を模索しています。留学先での経験やイノベーションプロモーター教員への思いについてお話をうかがいました。
- プロフィール
-
医歯学総合研究科
遺伝子細胞検査学分野
准教授
鈴木喜晴先生
研究分野について
先生が専門とされている領域や研究内容について教えて下さい。
- 鈴木:
- 私は学生の頃から細胞接着分子という細胞接着における分子間の結合様式に着目した研究をしています。幅広い細胞接着分子の中で最初は細胞外マトリックス分子に関する研究に携わりました。
細胞外マトリックス分子とは細胞の外周に形成される線維状の構造体を形成する分子または細胞外微小環境を形成する分子の総称で、例えば組織の基底膜に存在するラミニンという細胞接着性タンパク質が細胞に結合することによって細胞にシグナルを誘導し、細胞の増殖や分化をコントロールする性質を持ちます。コラーゲン、プロテオグリカン、ラミニンなど細胞外のタンパク質と細胞表面の受容体がどのような様式で結合しているのかを主に調べていました。現在も変わらず細胞接着分子に興味を持ち続け、研究を展開しているところです。2005年にアメリカに留学した時には研究対象が変わるかなと思ったんですけど、分子の種類は異なりますが、縁あってまた細胞接着分子を研究対象とすることになりました。留学先では細胞と細胞の間の膜タンパク質(テニューリン)に関する中枢神経系での細胞接着を研究の対象としていました。紆余曲折ありましたが、一貫して同じ研究を続けています。
細胞外マトリックス分子について面白いと感じるのはどのようなことでしょうか。
- 鈴木:
- 細胞外マトリックス分子は、所属していた研究室の指導教官の研究だったのですが、機能が多岐に渡り未解明なことが多く、研究を進めるにつれてその魅力にハマっていきました。細胞外に存在するラミニンというタンパク質が基本的な個体の発生の過程で色んな組織の細胞の増殖や分化に直接作用します。ラミニンの遺伝子に変異が生じることによって、先天性の疾患を発症させたり腫瘍の原因にもなります。ラミニンが癌化を促進するということも分かっています。
膜タンパク質・テニューリンの研究について教えて下さい。
- 鈴木:
- 留学先で私達が同定した遺伝子/タンパク質は、細胞と細胞の間の細胞間接着を担う膜タンパク質なんですが、始まりは偶発的に得られた遺伝性の変異型マウスの発見でした。誰が見ても明らかなほど下半身が震えるマウスが誕生したんです。意図的に作ったものではなかったので、当時はマウスが震える原因が分かりませんでした。私がちょうど研究室に参加したタイミングで原因を突き止めるというテーマが与えられました。時間かかりましたが、最終的には震えの元となる遺伝子テニューリン4を同定することができ、細胞間の接着を担う膜タンパク質をコードする遺伝子が原因であることを突き止めました。中枢神経は、多数の神経細胞(ニューロン)とグリア細胞(神経膠細胞)から構成され、神経細胞の集まりは灰白質、神経線維の集まりは白質と呼ばれています。震えるマウスには白質組織で神経細胞の軸索を被っている髄鞘の形成が顕著に減少、欠落していることが分かりました。
研究の対象となる疾患にはどのようなものがありますか。
- 鈴木:
- 中枢神経系の髄鞘はオリゴデンドロサイト、末梢神経系の髄鞘はシュワン細胞によって形成されます。髄鞘はさまざまな神経機能を調節する役割を担っており、神経の活動に深く関わっています。神経的な震えなどの神経疾患、近年だと精神疾患にも大脳をはじめとする中枢神経系の白質の髄鞘形成不全が影響していることが判明しています。
具体的な疾患は髄鞘形成が関わってくる神経疾患で、一番有名な病気は厚生労働省の指定難病にもなっている多発性硬化症です。多発性硬化症は視力障害、感覚障害、認知症、排尿障害などを引き起こし、後天的な影響で髄鞘が欠落するという疾患です。他には、髄鞘の構成や因子などに遺伝的な異常が起きる先天性大脳白質形成不全症も有名です。先天性大脳白質形成不全症は11種類の病気が発症することが特定されており、眼振、発達遅滞、痙性四肢麻痺を病状とするペリツェウス・メルツバッハ病が代表的な病気として研究発表されています。今後注目していきたい分野は精神疾患ですね。精神疾患は色んな分野で研究が進んでいますが、髄鞘の形成不全や脱髄を介して精神疾患を研究している例は少ないです。しかし、遺伝的な解析を行っていくと、ある程度の割合で確実に髄鞘関連の遺伝子に変異を持つ精神疾患患者が見られます。私が注目しているのは、テニューリン4が関わる双極性障害や統合失調症です。これら精神疾患における分子メカニズムを解明して、診断薬や治療薬にアプローチできるような研究に広げていきたいと思っています。
産学連携について
産学連携のご経験についてお伺いさせて下さい。
- 鈴木:
- まだ産学連携に携わったことはありません。私は理学部出身なので現象のメカニズムを解明する基礎研究に興味があり、研究してきた時間の大半を使ってきました。研究を実用化するために臨床の現場に応用していきたいと常々考えていますが、現在は基礎的な研究がほとんどなので企業と一緒に共同研究する機会がなかなか得られなかったと思います。
先生はアメリカで研究した経験をお持ちですが、産学連携について取り組みの違いを感じることはありましたか。
- 鈴木:
- アメリカにいた時はポスドク(博士研究員)だったので、直接企業とのやり取りはなかったですが、企業と研究室の距離感が近かった印象を受けました。私はアメリカ国立保健衛生所(NIH)の歯学・頭蓋顔面学研究所にいましたが、年に2回企業がキャンパス内にブース出展するフェスティバルがあり、多くの人が参加してにぎわっていました。直接企業の方と触れ合い、実験や研究の話を身近にできてよかったと思います。
企業から研究室の主宰者(PI)の名前を教えて欲しいと言われたり、PIから「企業から問い合わせがあったよ。鈴木先生につなぎますね」と声をかけられるなど、企業が進んで研究者や最先端の研究内容や情報を吸い上げて積極的にコミュニケーションをしかけていました。10年以上前のことですから、おそらく今はインターネットやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)など色んな方法を使ってフットワーク軽く動いているのではないでしょうか。オープンイノベーション機構が開催して下さるイベントに加えて、日本の大学はなかなか難しいかもしれませんが、もし似たような取り組みがあれば、日常的にあまり企業と交流をしない我々のような基礎研究の研究者でも気楽に足を運べると思います。新しい出会いから何か生まれることもあるかもしれませんね。
産学連携で企業に求めることはございますか。
- 鈴木:
- アカデミアだけでは実現できないことが企業の方々の協力によって可能になってくるはずです。応用研究でも例えば治療薬・診断薬などの開発はアカデミアだけでやっていくには限界があります。企業との共同研究は優れた研究成果が生まれることを促進するだけでなく、製品化・実用化につながるイノベーションを起こしたいですね。
プロモーターとしての取り組み
今回イノベーションプロモーター教員になった理由を教えて下さい。
- 鈴木:
- 所属している科の上司から勧められたのがきっかけです。私としても企業と接点を持つ機会が無かったことにもどかしさを感じていました。研究内容をより発展させていくために私達もオープンになって企業と共同研究を進め、持っているノウハウを応用できるようなことがしたいと考えていました。お話をいただいた時は「ぜひやってみたい」と二つ返事で快く引き受けました。
共同研究をするにあたってどのような進め方を考えていますか。
- 鈴木:
- もちろん明確なゴールが最初にあれば色んなことがやりやすいはずですが、「こうあるべき」というとっかかりは私の中では決めていません。何かきっかけがあればどんなことでもチャレンジしてみたいです。
先生から企業の方に対して情報を発信していく機会はありますか。
- 鈴木:
- 特になく、学会発表ぐらいですね。興味を持って観にきて下さる企業の方はいらっしゃいますが、今のところはまだ共同研究まで発展していません。
研究を通じて実現してみたいことはありますか。
- 鈴木:
- 自分の研究がもっと応用されるようにしていきたいです。脳科学の上で情報の伝達と処理を担う神経細胞が主役なのは間違いないですが、中枢神経系でのグリア細胞の機能も近年より注目されてきています。髄鞘もグリア細胞の一種が形成するものになります。髄鞘形成やグリア細胞に着目した研究を展開していくことで、今まで見えていなかった新しい切り口で脳科学を捉えていくことができるかもしれません。
加えて、疾患の診断や治療法の確立にも役立てる可能性もありえます。また、健康上の問題で日常生活が制限されずに生活が可能な「健康寿命」を延ばす方法もこれからの日本社会の中でとても重要になってきます。特に老化とともに髄鞘を成分とする白質の萎縮が、思考能力や記憶、学習などの低下と相関することが分かっており、私達の研究を深めることで対処法も発見できるかもしれません。精神疾患や神経疾患だけでなく、日常生活にも切り込んでいけるように研究していきたいです。興味を持って下さる企業がいらっしゃればぜひお話しをしてみたいですね。
企業の業種などに何かご希望はありますか。
- 鈴木:
- もちろん製薬会社が筆頭にあがりますが、食品関連の企業ともディスカッションしてみたいと思っています。面白いアイディアが浮かんだり、市場で喜ばれる製品が思いつくかもしれません。
アカデミア同士の研究で良かった点はありますか。
- 鈴木:
- アカデミア同士の共同研究は様々な研究室の方々と国内外問わずに進めています。共同研究をすることで自分達が持っていない技術やツールを活用させてもらえるので、研究の幅が広がり厚みがぐっと出て良い学びにもなります。共同研究は今度も継続していきたいです。
共同研究で大変だった思い出などありますか。
- 鈴木:
- 特に大変だった経験はありませんが、海外の研究室と一緒に研究をする時はお互い感覚や考え方が違うところもありました。苦労とまではいかないですが、時間的なことやルールなどお互いが理解し合うまでに何回もやり取りしなければいけないことはありました。
最後に
先生の趣味を教えて下さい。
- 鈴木:
- 趣味はバドミントンです。学生の頃からずっと続けています。留学先のアメリカでも、東海岸はアジア人が意外と多く住んでいるので、意外にもバドミントンができる場所が結構ありました。日本にいた時よりもアメリカの方がラケットを握る時間が長かったかもしれません(笑)。今は新型コロナウイルスの影響で活動を控えるようにしていますが、いつも近所の学校施設を使って練習しています。大会などには出ていませんが長く続けていきたいですね。
ありがとうございました。
CONTACT
東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。
