INTERVIEW
研究者インタビュー
2025.04.17
研究者インタビュー
Vol.72
ディープラーニングによるPET/CT装置の高画質化を産学連携で研究 新しいPET製剤開発や他科との共同研究にも意欲
第三期プロモーター教員

日本人の死亡原因でもっとも多い「がん」。従来のCT・MRIでは発見が難しかったとされるがんも早期に見つけられるPET検査に注目が集まっています。今回は、診断で使われる画像やPET/CT検査の画像高画質化を研究している土屋純一先生にインタビュー。産学連携での研究やプロモーター教員として挑戦したいことを聞きました。
- プロフィール
-
東京科学大学病院
放射線診断科
准教授
土屋純一先生
私が聞いてみました
-

-
医療イノベーション機構イノベーション推進室
インタビュアー詳細
URA(特任准教授) 磯部 洋一郎
研究について
所属分野について教えてください。
- 土屋:
- 私の専門分野は、画像診断です。現在は、画像を通じて病気の診断や治療効果を判定する放射線診断科に在籍し、研究と臨床に従事しています。画像と言ってもさまざまあり、X線やCT、MRI、超音波検査(エコー)に加えて、PET(陽電子放出断層撮影)のような核医学検査が挙げられます。画像診断とは別に、当科の立石宇貴秀教授の専門分野でもある核医学検査の研究にも注力しています。

核医学検査とはどのようなものでしょうか。
- 土屋:
- がん細胞や活動性の高い病変は、エネルギー源であるブドウ糖の代謝(糖代謝)が盛んです。そこで、ブドウ糖に似た物質である放射性医薬品(FDG)を体内に投与し、特殊なカメラで撮影・画像化することで、悪性腫瘍(がん)や炎症を見つけたり、転移、再発の診断にも非常に役立ちます。また、部位別のがん検査と異なり、一度に全身の状態を調べることが可能で効率的。予想外の位置に転移したがんの発見につながるケースもあります。
大学卒業後に放射線診断科を選ばれた理由を教えてください。
- 土屋:
- 学生の頃は精神科に興味があったり、横浜南共済病院での研修時は内科が好きになり、正直どの分野を専門にするか悩んでいました。本学に戻った時にさまざまな診療科で研修をさせていただき、1つの臓器・領域に特化するよりも他の科と連携をしながら全身の臓器や疾患の治療、研究ができる放射線診断科が私の性分に合っていて、魅力的だなと感じました。結果として、カンファレンスなどで各科の先生と話す機会に恵まれ、豊富な症例をもとに研究ができており充実した日々を送っています。
放射線診断科と放射線治療科の違いを教えてください。
- 土屋:
- 主に、体の外から放射線を照射して、がん細胞を死滅させる治療を行うのが放射線治療科です。放射線診断科は、撮影した画像検査の解析が中心で、血管内にカテーテルを挿入して病変を調べる血管内治療(IVR)にも取り組んでいます。似た名前で確かにややこしいですよね(笑)。
疾患や治療法の対象が幅広くて大変だったりしませんか。
- 土屋:
- 新しい薬剤や治療法が出た場合に、画像にどのような影響がでるのか知る必要があります。学ぶことは多いですが、画像を通して沢山の疾患に触れることができるので、興味深いです。
産学連携について
産学連携での研究内容を教えてください。
- 土屋:
- 従来と比較し、きれいな画像を撮ることができ、短時間撮影も可能な半導体PET-CT装置を大手企業機器メーカーから導入し共同研究を行っています。現在のPET画像もかなり綺麗で鮮明ではありますが、よりノイズを低減し、病巣をひと目で診断できる画像の実現を目指してデータを提供したり、ディープラーニング(深層学習)を用いた高画質の画像生成法を模索中です。他にも、投与する薬の量を減らしたり、被曝を低減する方法を探ったり、患者さんと向き合う医師が判別しやすい画像を追求しています。
産学連携を通じてどのような相乗効果を感じていますか。
- 土屋:
- 本学はPET検査の実施数が他施設より多く、企業と研究室が持っているノウハウやデータの相互利用が進めば、研究にも必ずプラスになるはずです。画質の評価方法や装置のソフトウェアで分からないことも直接相談できますし、装置を使っている立場から意見や要望を伝えられるので、信頼も厚く、製品の改良に反映しやすいと喜びの声もいただいており、企業に寄り添いながら良好な関係性を築いています。

別の診療科の先生とも共同で研究をしていると聞きました。
- 土屋:
- 当期のプロモーター教員でもある臨床解剖学分野の室生暁先生と一緒に、解剖の課題を解決するためにCTやMRIの画像診断の知見をお伝えしたり、他の科の先生とも治験を行う機会がありました。
その他の研究について教えてください。
- 土屋:
- 日常臨床で用いられるFDG以外にも、アミノ酸のPET製剤を用いた画像検査、低酸素環境を検出するPET低酸素トレーサー(FAZA)による低酸素イメージングなどに取り組んでいます。がん細胞の治療において、低酸素環境は放射線治療の効果を下げると言われていますが、他の疾患においても低酸素環境が治療に対する反応性や予後などに影響する可能性があります。低酸素イメージングの情報を追加することで、それぞれの腫瘍や炎症などの性状、環境に合わせた治療が実現できるように研究を続けていきます。
イノベーションプロモーター教員について
プロモーター教員になったきっかけを教えてください。
- 土屋:
- 所属している分野以外の先生とお会いしたり、研究の内容を直接聞いてみたいと思っていたので、立石教授からお声がけいただいたタイミングで即決しました。2024年10月、東京工業大学との統合で工学系の先生たちが一緒になり、専門領域も広がった。連携を深めつつ知見を広げ、先生たちが抱える画像診断の悩みや困り事を解決できるように、今の立場を研究に活かしたいと考えています。
将来どのようなチャレンジをしてみたいですか。
- 土屋:
- 産学連携を通じて、医療機器や検査装置も研究と同じく、日々の改善やアップデートによって開発が行われていることに気がつきました。企業との共同研究の経験や実体験を他の診療科の先生と共有し、産学連携に興味がある先生の後押しができたら嬉しいですね。今後は、学内の研究・最新の診療動向を紹介するBB(Blue Bird)セミナー(水曜日不定期開催)に参加したり、近いうちに登壇できたらと考えています。医療イノベーション機構から届くお便りや連絡は、有益な情報であふれていて私にとって貴重な情報収集ツールの1つです。ただ、産学連携では著作権の手続きや、倫理審査の申請書作りなど骨の折れる作業に直面することもしばしば。1つ願いが叶うとしたら手続きや書類対応をスタッフの皆さんにサポートしてもらえると嬉しいです。もし実現できたとしたら、研究や診療の時間にあてられるので大変助かります。
最後に
週末やお休みの日はどのように過ごされますか。
- 土屋:
- 仕事終わりや休みの日は家族と過ごす時間を大切にしています。子どもが小学校に上がったばかりなので、授業で習った内容や友達と遊んだ話を聞いたりしてあたたかく成長を見守っています。私は昔からミステリー小説が好きで、特に「百万ドルをとり返せ!」や「ケインとアベル」を書いたジェフリー・アーチャーの作品はおすすめです。週末は家族と書店に行っています。
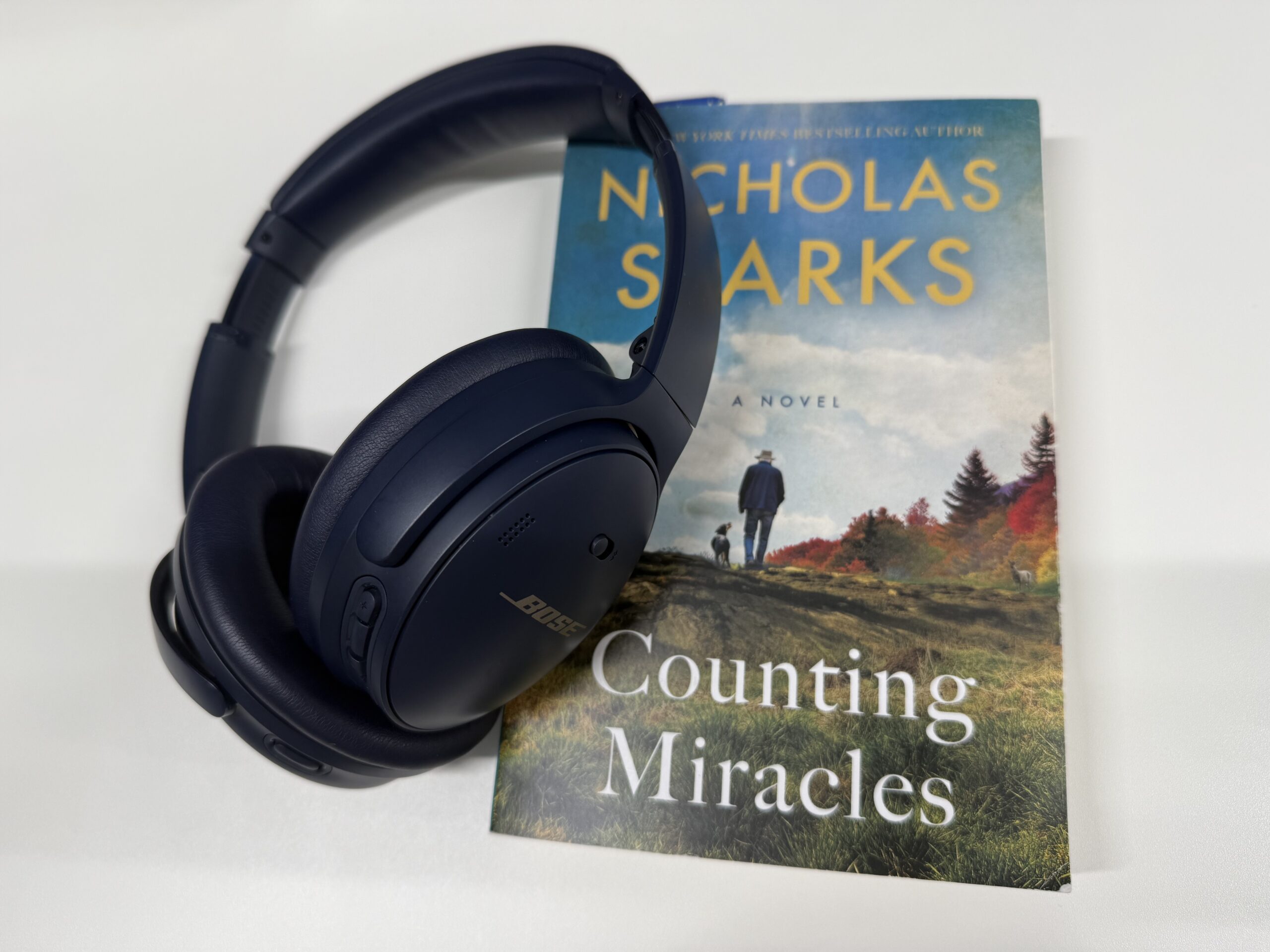
先生にお会いしたい方、研究プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください
医療イノベーション機構
openinnovation.tlo@tmd.ac.jp
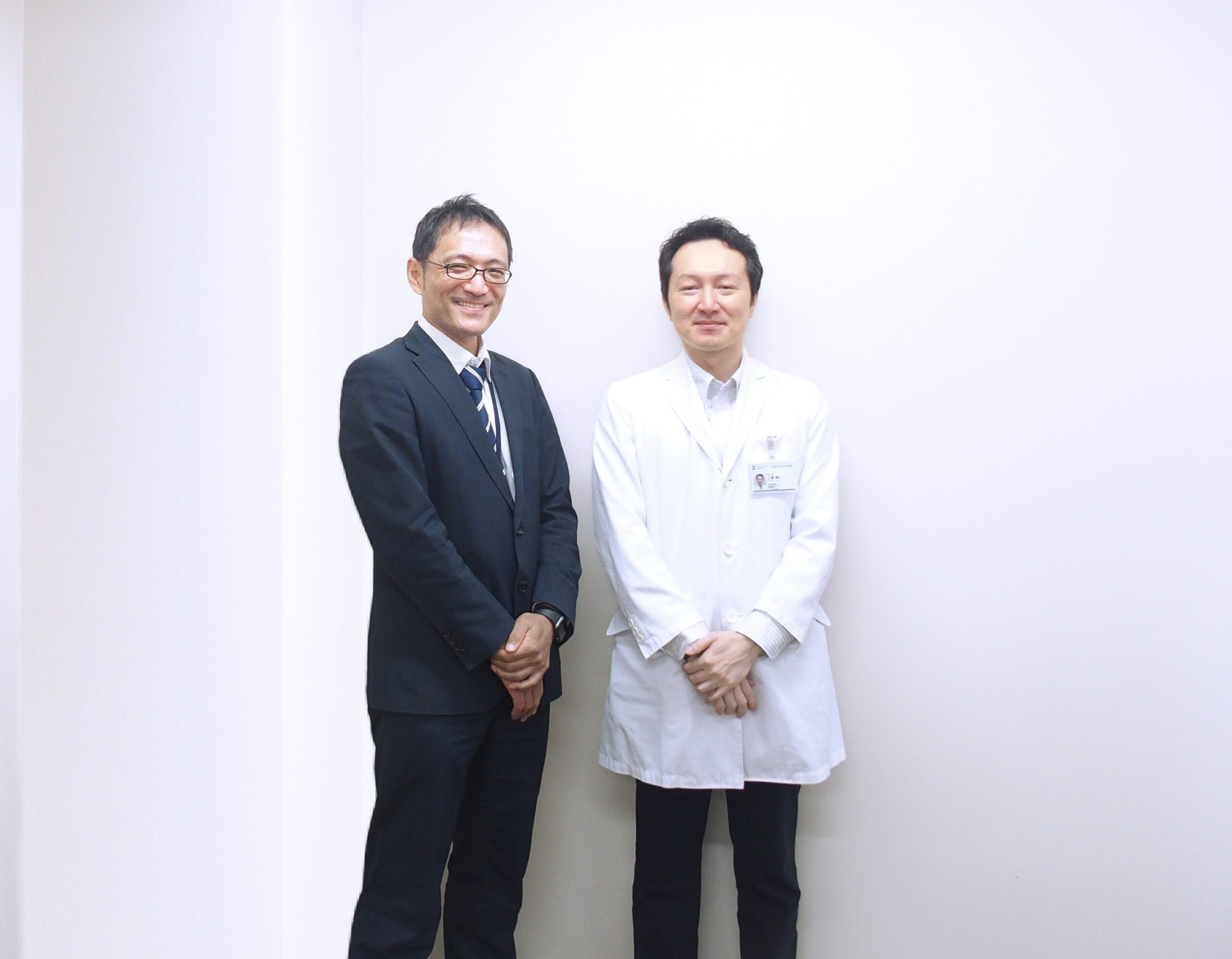
CONTACT
東京科学大学医療イノベーション機構に関するお問い合わせ、お申し込みは下記フォームにご入力ください。
